| ■目次 |
|
|
|
| ■太陽電池材料 |
|
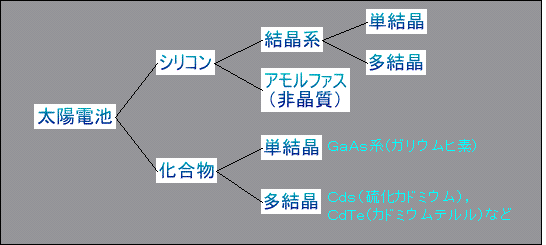 |
太陽電池の材料と種類は上記の図のようになります。
開発中のものも含めるとさらに多岐にわたりますが、ここでは現在普及が進んでいるもの、主たる開発動向に的を絞ってお話します。
なかでも住宅用途をはじめ主流となっているのはシリコン結晶系材料です。そしてどうしてシリコン結晶系太陽電池が主流であるのか,単結晶と多結晶はどう違うのか、またどうやって太陽電池は作られているのか、ここで順次お話してゆきたいと思います。
|
| 目次へ |
| ■なぜシリコン系なのか |
日本の総電力消費をまかなうためには四国の二分の一から四分の三の面積の太陽電池が必要だそうです。太陽電池は太陽の光をエネルギーに変換する効率が低いため、相当量のパネルが必要とされるわけです。太陽電池を今後の新エネルギーと位置付けるならば、資源寿命が豊かであること、環境へのインパクトが少ない、といった条件がおのずとあげられるでしょう。
まず、資源寿命の点から考えたときに、シリコン(SI)は地球上の元素として酸素についでもっとも豊富(重量比)です。
もちろん、太陽電池材料としてシリコンを用いる際にはエレクトロニクス材料に匹敵するほどの高純度を条件としますし、原材料となる珪石の産地も限られていますが、地球上に豊富に存在する材料には安定供給の可能性を秘めてはいないでしょうか。
また、少なくとも材料レベルで考えたときには、岩石や植物の構成物質であるシリコンは、猛毒のカドミウムやヒ素とひきかえ圧倒的に人体や環境に有利であります。
|
| 目次へ |
| ■単結晶と多結晶(シリコン結晶系) |
|
|
 |
 |
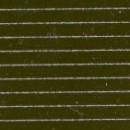 |
|
|
単結晶太陽電池(昭和シェル例)
|
|
単結晶拡大
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
多結晶太陽電池(シャープ例)
|
|
多結晶拡大
|
|
これらがもっとも普及している太陽電池タイプです。上の節でお話したような事情の他に技術上、コスト上、性能上これらが主流となっています。シリコン結晶系太陽電池は写真のような外観をしていてそれぞれに特徴をもっています。
- 単結晶(Single Crystal)
実用太陽電池として最も古い歴史を持っています。
太陽電池が光を電気に変換する効率を”変換効率”というのですが、単結晶太陽電池は変換効率が比較的に高いのが特徴です。
そしてこのタイプが世界市場でもっとも多く生産されてきました。しかし、下記にお話する多結晶と比べて原材料の生産に大量の電力を要し、製造設備への投資額も大きく、コストがかかるという弱みをもっています。そうした問題があって、最近になって多結晶にシェアの首位を譲っています。
外観上は写真に示すように漆黒の板です。横に走る線は電極です。
そして、金のインゴットや水晶と同じように、割れ目や切れ目がなく整然と原子が並んでいますので落ち着いた風合いとなります。
あるメーカーさんは、「うちの単結晶は太陽電池界のベンツですから〜」と言ってましたが、確かに発電性能といい期待寿命といい、すべての点でもっとも優れた太陽電池です。その信頼性から公共事業や商用電力のない僻地での電源供給に活躍してきました。
- 多結晶(Poly Crystal)
住宅の系統連系で市場を席巻している太陽電池です。
単結晶にあるような複雑な製造プロセスを簡略化し、少しでもコストを低減化させようとしたのが多結晶シリコンです。
細部を見るとよくわかりますが、小さな結晶の集まりからなっています。ひびのように見えるのは、小さな単結晶の粒がびっしり固まっているようなものだとお考えください。
単結晶にあるような、種結晶から成長させてインゴットを作る工程がないことと、一枚一枚のセルの大面積化が可能となっている点がコストの削減と住宅市場での普及の背景となっています。
同面積のセルでは性能面で単結晶にかないませんが、モジュールとして用いる際には限られた面に一杯にセルを並べることで単結晶に遜色のない面積当り出力を可能としています。
太陽電池の業界では”変換効率”という言葉が念仏のように繰り返されますが、セル単体で言っているのか、モジュール単体で言っているのか、はたまた実験室レベルで言っているのか、設置の際の屋根面積に対して言っているのか、注意が必要です。
どのメーカーさんも自分のところの商品が一番いい、といいたいですものね。
|
| 目次へ |
| ■アモルファス太陽電池(シリコン非晶質) |
|
 |
 |
 |
|
|
アモルファス太陽電池(クボタ例)
|
|
アモルファス拡大
|
|
アモルファスは非晶質とも呼ばれていて全く結晶性のない、つまり規則的な並びのない原子の集団のことです。
身近なところでは電卓がありますね。結晶系は可視光に反応しますがアモルファスは特に蛍光灯下で性能を発揮する特色があります。
モジュールの変換効率が低いために電力用途としては結晶系にかないませんが、その製造プロセスは反応温度が低いため結晶系ほど電力を必要とせず、所要資源量も数百分の一程度と少ないためにコスト削減の旗手として注目されています。
また、可とう性(ぐにゃぐにゃ曲げることができる)のあるモジュールを作ることができますので曲面をした屋根や美観を重んじる場所での使用が可能です。
一方、紫外線による劣化がありますので、出荷時に定格以上の出力のものが求められます。
つまり、設置直後は定格以上の出力があるのですが、ある一定期間は歳月が経過するにつれ出力が低下するという弱点があります。変換効率もまだまだ低いものです。
したがって結晶系と同等程度の出力を得ようとすると結晶系の1.5倍程度の設置面積が必要との試算があります。
モジュール単体の多くは暗色で屋根一体型となっていますので、この場合の設置後の外観は屋根と見分けがつかないほどになります。
特筆すべきこととして、サンヨーの製品のように単結晶セルとアモルファス層をサンドイッチして面積当りの発電量を飛躍的に向上させたものもあります。
 サンヨーのHIT。単結晶同様の外観。面積当たり効率が高い。 サンヨーのHIT。単結晶同様の外観。面積当たり効率が高い。
|
|
| 目次へ |
| ■化合物太陽電池 |
高効率をめざして作られていますが、電力用途としては資源量や製造コストの問題もあり、特殊用途や実験室レベルにあるものが多いといえます。
特にガリウムヒ素やインジウムリンなどの単結晶は宇宙用途などに用いられ、効率と信頼性にすぐれます。
この他、硫化カドミウムやカドミウムテルルなどの多結晶は電卓や時計用途の民生用で用いられます。
これらはいずれも電力用途の大量生産の観点からは、シリコン結晶系に比べ資源量が少なく、有害物質を含む点が気になります。
|
| 目次へ |
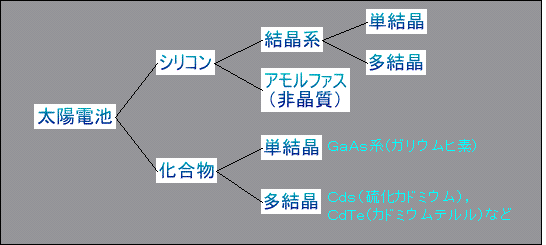

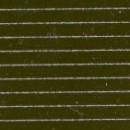




 サンヨーのHIT。単結晶同様の外観。面積当たり効率が高い。
サンヨーのHIT。単結晶同様の外観。面積当たり効率が高い。